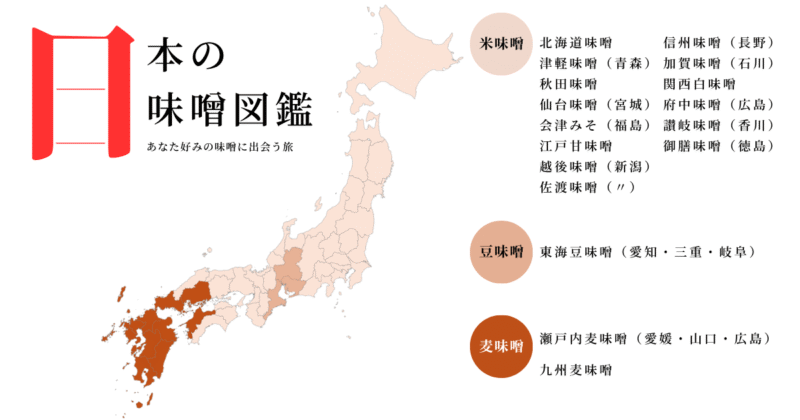やってきました中部地方!
どうですか?日本の真ん中を過ぎてきましたよ!
旅の疲れはありませんか?
さて、今回の旅は中部地方を甲信・東海・北陸の3ブロックにわけてご案内します。
-
さっぱり辛口で懐の深い 信州味噌(長野)
-
麦麹も生かしたまろやかな 甲州味噌(山梨)
-
長期熟成でコク深い 豆味噌(愛知・八丁味噌)
-
米麹たっぷり、魚介とも響き合う 北陸のみそ(加賀・越中・越後・若狭)
無添加・天然醸造にこだわる味噌蔵、そして味噌の個性が光る郷土料理まで。
あなたの“推し味噌”が見つかりますように。
これまでの旅の疲れを癒やすため味噌をひと舐めして、さあ出発!
甲信エリアの味噌の特徴
長野県 信州味噌
全国生産量の約半分を占める、言わずと知れた日本を代表する味噌が信州味噌です。
- 原料と色合い
主な原材料は米麹・大豆・塩。米麹と大豆をほぼ同量で配合し発酵させます。
仕上がりは山吹色や淡い黄褐色で、熟成期間が長いものは赤みを帯びることもあります。 - 味と香り
すっきりとした辛口で塩分は約12%前後。
大豆の旨味と米麹のほのかな甘みがバランスよく、クセが少ないため毎日のお味噌汁に使いやすいのが特徴です。
熟成が進むにつれ、塩味の角が取れてまろやかさが増します。 - 製法と地域性
寒冷な長野県の気候を活かし、3ヶ月〜1年以上の長期熟成がおこなわれます。
天然醸造では寒暖差が香りや風味をより豊かにし、地域ごとの水や空気も味わいに影響します。
地元の大豆や米を使う蔵元も多く、土地の個性が表されています。
ー味噌と偉人ー
戦国武将、武田信玄は甲斐(山梨県)を本拠におき信濃国(長野県)で大豆の栽培と味噌作りを奨励しました。
味噌は保存性と栄養価が高いため、兵士たちの体力維持や士気向上に欠かせない兵糧としてとても重宝されました。
また、陣立味噌を考案するなど信州味噌の発展・普及に大きく寄与した人物なんです。
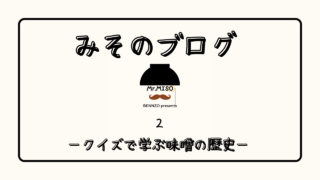
山梨県 甲州味噌
山梨県を代表するのは、米麹と麦麹を合わせて仕込む「甲州味噌」です。
- 原料と製法
大豆をベースに米麹と麦麹を半量ずつ配合し、まろやかなで優しい風味に仕上がります。
木桶を使った天然醸造・無添加の蔵が多く、半年〜10ヶ月以上じっくり発酵させるのが特徴です。 - 味わいと用途
クセが少なく自然な甘みとコクがあり、味噌汁はもちろん郷土料理の「ほうとう」にも欠かせません。
生味噌として流通しているものも多く、発酵が続くことで季節ごとの色や香りの変化も楽しめます。 - 地域性
山梨は山が多く米の栽培に限界があったため、大麦を活用した味噌文化が発展しました。
地元の大豆や穀物を使う蔵元も多く、自然環境と伝統が生み出した味噌と言えます。
長野県の味噌蔵
全国の味噌生産量の約半分を担う長野県は、まさに「味噌大国」。県内には100を超える味噌蔵が点在し、大手メーカーから地域に根差した小規模蔵まで、多彩な信州味噌が造られています。
老舗の木桶仕込みから最新設備を備えた工場まで、信州の発酵文化に触れる楽しみが広がっています。
味噌蔵ごとの詳細は「長野県味噌工業協同組合連合会」の公式サイトで一覧できます。
本当に参考になる情報がたくさんありますので、気になる方は是非ご覧になることをオススメします!
山梨県の味噌蔵
五味醤油(甲府市)
1868年(明治元年)創業。150年以上の歴史を持つ老舗味噌屋。
米麹と麦麹を半々に使ったまろやかな味わいは郷土料理「ほうとう」には欠かせません。
6代目とその妹が「発酵兄妹」としてワークショップやラジオなど食育活動にも力を入れ、伝統の味と文化を未来へとつなげています。
オススメは「甲州味噌(合わせ味噌)」です。
みそ工房の郷(笛吹市)
「家族に安心して食べさせたい」という想いから、主婦が始めた小さな味噌蔵。
山梨県産の青大豆を使い、加熱処理をせず1年かけてじっくり天然醸造した無添加味噌は甘みとコクが格別です。
味噌作り体験教室も人気で、自分で仕込んだ味噌を自宅で熟成させる楽しみも味わえます。
オススメは「特上米味噌」です。
長野県の郷土料理 五平餅
出典:農林水産省ウェブサイト
長野県木曽・伊那地方をはじめ、中部地方の山間部に伝わる伝統的な郷土料理です。
炊いたうるち米ををしっかり潰して、串に刺し香ばしく焼き上げて甘辛い味噌ダレを塗る素朴な味わい。
神事で使われる「御幣」に形が似ていることや、「五平さん」が食べていたことが始まりなど由来には諸説あります。
山梨県の郷土料理 ほうとう
出典:農林水産省ウェブサイト
平たい幅広麺をかぼちゃ、白菜、大根、にんじん、しいたけなど旬の野菜と一緒に味噌仕立ての汁で煮込んだ料理です。
豚肉なども加えることが多く、栄養バランスに優れた一品です。
戦国時代の武田信玄が陣中食(戦場食)として奨励したこともあり、「武田汁」と呼ばれた歴史があります。
東海エリアの味噌の特徴
中山道や東海道を往来する旅人の胃袋を満たしてきたのが、濃厚な豆味噌。
この地方では、信州味噌のような淡色味噌ではなく、大豆と塩だけを原料にした深いコクのある赤味噌文化が根づいています。
東海エリアは日本唯一の豆味噌の生産地。
特に愛知はその原点であり中心的な存在です。
岐阜や三重、静岡もとても個性的で素晴らしい味噌が揃っていますが、割愛させていただき愛知にスポットを絞りたいと思います。
- 豆味噌(赤味噌)の魅力
豆麹を使い1年から3年ほどの長期熟成が基本。
色は深い赤褐色で味は甘みを抑えた辛口で、独特の渋みと酸味が絡み合います。 - 赤味噌の代表格
愛知県岡崎市の「八丁味噌」は豆味噌の代表的存在です。
名物の味噌カツ、味噌煮込みうどんなど名古屋めしには欠かかせません。 - 赤だしが日常
家庭や飲食店で出される味噌汁はもちろん赤だし。
ごくごく当たり前の話なので割愛します。
ー歴史と偉人ー
東海地方の豆味噌は、戦国の乱世を生き抜いた武将たちの生命線でもありました。
織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・・・名だたる偉人たちは皆、豆味噌を愛し戦と人生を支えた糧となっていたのです。
その中でも愛知県の岡崎生まれの家康は、筋金入りの健康オタク。
故郷から取り寄せた八丁味噌を使った、具沢山の味噌汁を毎日食べていたそうです。
その結果、当時では異例の75歳まで長生きするという偉業を成し遂げました。
味噌パワー恐るべし!
東海エリアの豆味噌3選
八丁味噌
愛知県岡崎市八帖町発祥の伝統ブランド。
二夏二冬(2年以上)熟成させることで生まれる濃厚さと、渋み・苦みを含んだ奥深い味わいが特徴です。
岡崎城から八丁(870m)の地に蔵を構えた「カクキュー」と「まるや」の2社が、今も伝統の木桶仕込みを守り続けています。
三州味噌
愛知県東部、三河地方を中心に作られる豆味噌。
八丁味噌ほど長期熟成はさせず、比較的マイルドな仕上がりが特徴です。
渋みや酸味はあまりなく、家庭料理や日常の味噌汁にも使いやすい”親しみある赤味噌”です。
三河味噌
同じ三河地方でも、地域や蔵ごとに製法や味わいに微妙な違いがある豆味噌。
八丁味噌と重なる部分もありますが、仕込みや熟成の工夫で風味が異なり”地元色の強い味噌”として愛されています。
農家や地域の食堂で代々受け継がれてきた、土地の味を映す赤味噌です。
愛知県の味噌蔵
東海地方の豆味噌文化を語るうえで外せないのが、愛知県。
中でも岡崎市は「八丁味噌」の発祥地として知られ、今も昔ながらの木桶仕込みを守る蔵元が点在しています。
その魅力をより深く知るには、公式ポータルサイト 「あいち発酵食めぐり – 味噌 Aichi Miso」 が最適です。
愛知県公式:味噌 Aichi Miso
ここでは、家康が生涯愛した八丁味噌の歴史や、木桶と石積みでじっくり熟成させる伝統製法、そしてカクキューやまるやといった老舗蔵の情報が紹介されています。
ぜひ一度ご覧になってください。
愛知県の郷土料理 味噌煮込みうどん
出典:農林水産省ウェブサイト
名古屋を代表する郷土料理が 味噌煮込みうどん。
八丁味噌を使った濃厚なスープに、塩を使わず小麦粉と水だけで打った硬めの麺を生のまま煮込むのが特徴です。
土鍋で熱々のまま提供され、鶏肉・ねぎ・油揚げ・卵など具材も豊富。食べ終わった後にご飯を入れて「おじや」にするのも地元ならではの楽しみ方です。
豆味噌のコクと強いコシの麺が織りなす、名古屋独自の一杯。これぞ“名古屋めし”を代表する味わいです。
北陸エリアの味噌の特徴
雪国・北陸は寒さを味方につけた発酵文化の宝庫。
米麹をたっぷり使い、保存性と風味を兼ね備えた味噌が各地に根づいています。
北陸味噌の共通点
- 米麹を多く使う・・・寒冷地でも発酵を進める工夫
- 魚介との相性がいい・・・塩分や水分の調整で海の幸と合わせやすい
- 豊かな香りと個性・・・赤系・辛口をベースに県ごとに味わいやコクが違う
福井県 若狭味噌
福井県若狭地方を代表するのが若狭味噌。
大豆:米麹が1:2と麹歩合が高く塩分は控えめ(約11%)なのでまろやかな甘味があります。
国産米・国産大豆を使った天然熟成で、6ヶ月以上じっくり発酵。
安心・無添加を掲げ、地元の学校給食にも提供されていて地域に根づいています。
やさしい甘みと米麹の香りが魅力で、焼き魚や煮物とも相性抜群です。
石川県 加賀味噌
加賀味噌は加賀百万石の食文化を支えた歴史ある味噌。
米麹の割合が高く、甘みとコクが際立ちます。
伝統的には塩分が高めの辛口でしたが、近年は減塩傾向にシフトしています。
長期熟成で赤褐色に色づき、魚介との相性がいいのが特徴です。
用途は幅広く味噌汁だけではなく、田楽やラーメン、魚料理などにも活躍。
江戸時代には軍需保存食として重宝され、今もなお地域の食文化を象徴する存在です。
富山県 越中味噌
富山の越中味噌は、赤色系辛口で米麹を多く使ったパワフルな味噌。
水分を多めに仕込み、柔らかく溶けやすいため味噌汁にすると麹粒が浮く「浮き麹」見られます。
昔は塩分16%前後と高めでしたが、現在は12%前後に落ち着いています。
2〜3年かけて熟成させるため旨味が濃厚で、白エビやホタルイカなど富山湾の海の幸との相性抜群。
新潟県 越後味噌・佐渡味噌
越後味噌
米どころ新潟を代表するのが越後味噌。
赤色系で辛口が基本ですが、最大の特徴は「浮き麹味噌」。
米麹を多用することで白い麹粒が残り、爽やかな甘味と旨味が感じられます。
上越は淡色で麹感が強く、中越・下越は赤みが強く塩味もしっかりと地域差があるのも魅力。
佐渡味噌
新潟県佐渡島で育まれてきた佐渡味噌は、赤系辛口の米味噌。
大豆に対して米麹を多めに配合し、杉樽でじっくり長期熟成させることで深みのあるコクと香りを生み出します。
粒をすりつぶして仕込む「こし味噌」タイプで舌触りはなめらか。
江戸時代から作られ、明治には日本海航路を通じて北海道へも出荷された歴史ある味噌です。
北陸エリアの味噌蔵
福井県
米五(こめご)みそ(福井市春山)
1831年(天保2年)創業。
永平寺御用達として知られる福井の老舗味噌蔵です。
国内産の米と大豆、地元の水を使い、木桶でじっくり熟成する昔ながらの製法を守り続けています。
米五のみそは、甘口〜中辛の米麹みそが中心。
素朴ながらもコク深く、永平寺の精進料理や学校給食でも親しまれるやさしい味わいです。
さらに、味噌づくり体験施設「みそ楽」を運営し、家庭用の手作り味噌セットも展開。
伝統を守るだけでなく、味噌文化を次世代へつなぐ取り組みも魅力です。
オススメは2年熟成の最高級味噌「ほまれ」です。
石川県
菊田味噌(金沢市)
1895年(明治28年)創業。
金沢市大野町で加賀味噌を作り続けてきた老舗。
米麹を多く使い、じっくり熟成させた濃厚で米の甘みが広がる味わいが特徴です。
定番の「米こうじみそ」は地域で長く愛され、地元のラーメン店や食堂でも親しまれています。
味噌蔵を改装した「味噌蔵カフェきくや」では、味噌田楽や地元食材を使ったメニューが観光客にも人気。
130年にわたり加賀味噌の伝統を守り、日常の食卓から観光まで地域文化を発信する蔵元です。
オススメは「加賀味噌1.7kg」です。
富山県
南日(なんにち)味噌醤油(富山市)
1889年(明治22年)創業。
富山市に根づく老舗の味噌・醤油蔵。
戦災を乗り越え、130年以上にわたり麹づくりを中心に発酵食品を手がけてきました。
米麹をたっぷり使った味噌はもちろん、醤油や甘酒・塩こうじなど幅広く展開しています。
伝統的な木桶仕込みと最新設備を融合させ、品質と安全性を徹底的に追求。
味噌ソムリエ・一級技能士の当主が率い、地域の食文化を支えつつ次世代へ技術をつなぐ姿勢も魅力です。
富山の自然と人に寄り添う発酵蔵として、南日味噌醤油は今も「食卓に健やかさと豊かさ」を届けています。
オススメは「特選桜いなかみそ 1kg」です。
新潟県
丸久味噌(上越市)
1850年(嘉永3年)創業。
上越市で約170年の歴史を持つ老舗蔵です。
米どころ新潟の良質な米を丁寧に麹に仕立て、北海道産大豆と国産塩を合わせ、杉桶で仕込む天然醸造の米こうじ味噌を守り続けています。
モットーは「原料に勝る技術なし」。63本の大桶に棲みつく蔵付きの菌が、華やかな香りとまろやかで深みある味を生み出します。
代表作「一途」は、健康志向の人々からも高い支持を得る最高級品。
伝統と品質へのこだわりを貫きつつ、新潟の発酵文化を全国に発信する蔵元です。
オススメは「純生味噌(粒)」です。
北陸エリア郷土料理
福井県 呉汁
出典:農林水産省ウェブサイト
福井の冬を代表する味噌料理が呉汁。
大豆をすりつぶした「呉」を味噌汁に加え、里芋やカブ、人参など季節の野菜と一緒に煮込む、滋味深い一杯です。
大豆の旨みと甘みが溶け込んだスープは、クリーミーで体を芯から温めてくれます。
精進料理としても伝えられ、報恩講などの行事で振る舞われることも多く、福井の食文化を象徴する存在です。
たんぱく質やイソフラボンなど栄養も満点。家庭ごとに味わいが少しずつ違う「おふくろの味」として、今も大切に受け継がれています。
石川県 きしず
出典:農林水産省ウェブサイト
祝いの席や祭りに欠かせない、石川県の伝統料理がきしず。
キャベツや麩、わかめ、大根などを下ゆでして、白味噌や辛子酢醤油で和えたシンプルながら華やかな一品です。
白味噌を使うと甘みとコクが際立ち、辛子や酢を加えれば爽やかさが引き立つ。
家庭ごとに味付けが異なり、バリエーション豊かな「おふくろの味」として親しまれています。
お正月や祭りなどハレの日に食卓を彩り、家族や地域の絆を感じさせる料理として今も受け継がれるきしず。発酵文化が根づく石川らしい郷土料理です。
富山県 ホタルイカの酢味噌和え
出典:農林水産省ウェブサイト
春の富山湾を彩る味覚といえば ほたるいか。
そのぷりっとした身を、まろやかな辛子酢味噌で和えたのが「ほたるいかの酢味噌和え」です。
ボイルしたほたるいかの甘みと旨み、わけぎやわかめの爽やかさ、そして酢味噌の酸味と辛子のアクセントが絶妙に絡み合います。
丁寧に目や口を取り除くことで、なめらかな食感と上品な味わいに仕上がるのもポイント。
日本酒の肴としても、ご飯のおかずとしてもぴったり。
富山の春を告げる定番料理であり、旬の恵みを味噌とともに味わう一品です。
新潟県 たけのこ汁
出典:農林水産省ウェブサイト
新潟の春を告げる代表的な味がたけのこ汁。
地元で「姫たけのこ」と呼ばれるチシマザサの若芽を使った味噌汁で、シャキシャキした食感と爽やかな香りが特徴です。
最大のポイントは サバ缶を汁ごと加えること。魚の旨味と脂が溶け込み、味噌のコクと合わさって滋味豊かなスープになります。
じゃがいもや玉ねぎ、にんじんなどの野菜も加わり、栄養満点。
春限定の味覚として家庭や集まりで親しまれており、地域の暮らしに根づいた「旬を味わう一杯」。
素朴ながらも深い旨味が楽しめる、新潟ならではの郷土料理です。
まとめ 中部地方のおさらい
甲信
長野=信州味噌…淡色〜赤系のすっきり辛口、毎日使いに“ちょうどいい”。
山梨=甲州味噌…米麹×麦麹の合わせで、まろやか&素朴なコク。
東海(愛知)
豆味噌の中枢。八丁味噌の二夏二冬熟成が生む濃厚なコクは名古屋めしの核。
北陸(福井・石川・富山・新潟)
米麹リッチ&発酵力強め。
福井=若狭味噌、石川=加賀味噌、富山=越中味噌、新潟=越後味噌・佐渡味噌
若狭のやさしい甘み、加賀の濃いコク、越中の“浮き麹”、越後・佐渡の辛口×香り。
時代が動いた天下分け目の戦い。
あなたにとって味噌の常識もまた一つ変わり始めたのではないでしょうか?
今回も推し味噌は見つかりましたか?
次回は「関東地方編」でお会いしましょう!お楽しみにー!
最後まで読んでいただき本当にありがとうございました!!